1757、色消しレンズ~ドロンド(英):アルケーを知りたい(556)
今回の話題は(A)物理学。
▼凸レンズ一枚の拡大ルーペを使うとき、像の周辺に薄く色がにじむことがある。そういった現象を解決するため屈折率が異なるガラスのレンズを組み合わせてにじみを消したのが色消しレンズ。ところでレンズは単数形でもlensとsがつく。
▼ドロンドの時代は、ガラスからレンズを磨きだしていたホイヘンス(1629 - 1695)やスピノザ(1632 - 1677)の時代からおよそ100年後。
▼ジョン・ドロンド John Dollond 1706 - 1761 イギリスの光学技術者
【教育】独学
【職業】絹織物業職人の息子として40半ばまで家業を継続。
1750(44)息子と光学機器製造メーカー・光学機器店「Dollond & Aitchison」を起業。家業で生計を立てながらレンズの研究と開発を進めていた。息子が先に専業メーカーと販売を始めたので、そこに合流する恰好だ。
1752(46)までは家業の絹織物職人をやっていた。想像するに、ドロンド家の将来を考えたとき、絹織物とレンズのどちらをとるか、よくよく考えたのだろう。
1761(55)国王の眼鏡技師。
【業績】1758(52)『光の異なる屈折率に関するいくつかの実験の説明』で色消しレンズを発表、その功績によりコプリ・メダルを受賞。
1761(55)王立協会の会員。
【同時代人】同じ年生まれにベンジャミン・フランクリンと日本で初めて人体解剖を行った幕府の医官・山脇東洋がいる。
【ネットワーク】
サミュエル・クリンゲンスティエナ Samuel Klingenstierna 1698 - 1765 スウェーデンの数学者。▼ジョン・ドロンドの屈折理論の誤りを指摘、自らも無色望遠鏡の発明に尽力。▼ドロンドはクリンゲンスティエナ指摘を受け入れて問題を解決した。
ベンジャミン・フランクリン Benjamin Franklin 1706 - 1790 アメリカの建国の父。雷のときに凧を上げて静電気の実験を行った物理学者。
山脇 東洋 1706 - 1762 江戸時代の医学者。日本で初めて江戸幕府の医官として人体解剖を行った。日本近代医学のパイオニア。
レオンハルト・オイラー Leonhard Euler 1707 - 1783 スイス生まれの数学者。1747(40)ガラスのレンズと水の組み合わせで色収差をへらす可能性を示唆。▼ドロンドはこれをヒントにレンズを組み合わせて色収差を減らし、特許を取得。しかし特許権の行使は控えた。
ピーター・ドロンド Peter Dollond 1731 - 1820 ジョン・ドロンドの息子。1763(32)トリプル・アクロマティック・レンズ(アポクロマート・レンズ)を発明。▼ピーターが光学機器事業を開始。その時点では、父はまだ家業の絹織物業を続けていた。しかし、息子の事業を見て、いてもたってもいられなくなった父親のジョンが参加し『Dollond & Aitchison』社を起業した。ピーターは父のジョンが取得していた特許を行使し、ビジネスを発展させた。
【似顔絵サロン】
〔参考〕
『理科年表2022』
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dollond
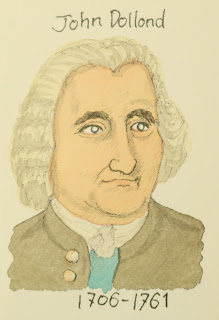








コメント
コメントを投稿