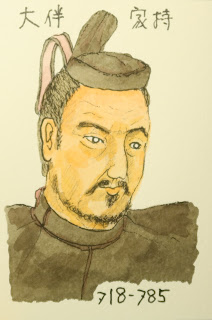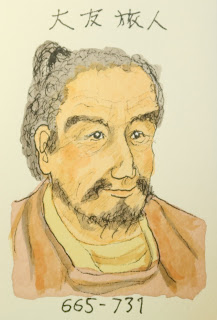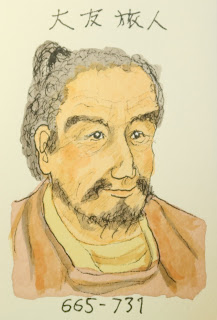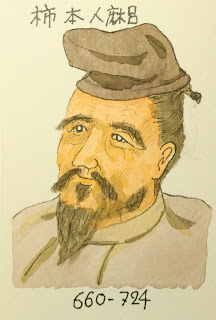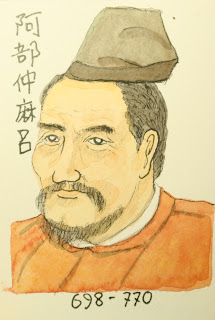大伴旅人の万葉集331-332番歌~アルケーを知りたい(1085)

▼今回の歌は、万葉集に収められた旅人の歌のうち二番目に出てくる作品。大宰府で詠んだ歌。今回は2の1。 ▼この歌が詠まれた背景:小野老 (おののおゆ) 朝臣が大宰少弐として大宰府に着任したので歓迎の宴席が設けられた。 ▼まず小野老が「 あおによし奈良の都は咲く花の にほふがごとく今盛りなり (万328)」で口火を切る。 ▼次に大宰府防人司祐の大伴四綱が「 やすみしし我が大君の敷きませる 国の中には都し思ほゆ (万329)」と「 藤波の花は盛りになりにけり 奈良の都を思ほすや君 (万330)」を詠み、次を旅人に振る。 ▼これを受けて旅人が詠んだのが331から335の歌。 ▼大伴旅人の和歌と*勝手に解釈 帥大伴卿(そちおおとものまへつきみ)が歌五首(はじめの二首) 我が盛りまたをちめやもほとほとに 奈良の都を見ずかなりなむ 万331 *私の盛りの時期はまた戻ってくるのでしょうか。すっかり参ってしまいましたから、奈良の都をまた見ることはないかも知れません。 我が命も常にあらぬか昔見し 象の小川を行きて見むため 万332 *私の命が長らえると良いのですが。というのも、昔見た奈良の象(さき)の小川をまた見に行きたいからです。 ▼ 大伴 旅人 おおともの たびと 665天智天皇4年 - 731天平3年8月31日 66歳。 飛鳥時代~奈良時代初期の公卿・歌人。父親は大伴安麻呂。妻は大伴郎女、百人一首6番歌の歌人・ 大伴家持 は息子。728(63) 大宰府に赴任、山上憶良・満誓らと筑紫歌壇を形成。 【似顔絵サロン】 〔参考〕 伊藤博訳注『新版 万葉集一』角川ソフィア文庫。 https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tabito2.html https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%BC%B4%E6%97%85%E4%BA%BA