計算力があれば原爆の実現可能性だって発見できる:MAUD委員会の教訓(1)
アルケーを知りたい(329) MAUD委員会(1)
今回の話題は(C)マンハッタン計画。
イギリスの歴史家のマーガレット・ガウイングさん(Margaret Gowing, 1921年4月26日 - 1998年11月7日)は、MAUD委員会を「史上最も効率的な委員会のひとつ」と評価した。
ここでは、原爆の実現可能性をフリッシュさんとパイエルスさんが発見した1940年3月を起点、MAUD委員会が解散した1941年7月を終点として、フリッシュさんの本に沿って数回にわたって見ていく。
経緯 フリッシュさんは、1934年から1939年の間、デンマークのコペンハーゲンにあるニールス・ボーア研究所にいた。しかし、1939年にナチスがデンマークに侵攻。ナチスから逃れるために渡英し、バーミンガム大学のマーク・オリファント先生の下に移る。このとき、同じようにナチスから逃れていたドイツ生まれのユダヤ人理論物理学者ルドルフ・パイエルスさん(32)と一緒になる。
2人はウランの核分裂を利用した原子爆弾が可能かどうか検討する。クラウジウスさんの式とフリッシュさんが考案したウラン分離システムの効率を使って計算する。結果は、可能。「原子爆弾はやはり可能だったのだ。このとき私たちはお互いを凝視して、初めて、本当にそう思った。At that point we stared at each other and realized that an atomic bomb might after all be possible.」(p.157、英p.126)
感想 今回は、フリッシュさんとパイエルスさんが計算で気づいたときの話だった。イギリス、ドイツ、アメリカの物理学者は核分裂の発見のあと、これを利用した強力な新型爆弾の製造ができるのではないか、と考えていた。時期も時期、WWIIが開戦するタイミングだ。ドイツがイギリスより強力な武器を手にするのはまずい。2人は自分たちで出した計算結果を見て、お互いを凝視する場面が印象的。
1822年、ポーランドのコシャリン生まれ。父は牧師兼小学校の校長。
父が校長をしている小学校で学ぶ。
1838(16)シュテッティン(現ポーランドのシチェチン)のギムナジウム。
1840(18)ベルリン大学入学。数学と物理学を学ぶ。
1844(22)ベルリン大学卒業。
1848(26)ハレ大学で博士。地上の大気の光学効果。
ベルリンのフリードリヒ・ヴェルダー・ギムナジウムで教師(物理、1850年まで)。
1850(28)ベルリン王立砲工学校で教授(物理学)。
1854(32)論文「力学的熱理論の第二基本定理の1つの改良型について」発表。熱力学第二法則を確立。
1855(33)チューリヒ工科大学で教授。
1857(35)兼任でチューリヒ大学で教授。結婚。
1865(43)チューリヒ哲学会で論文発表。熱力学の第一法則(宇宙のエネルギーは一定)、第二法則(宇宙のエントロピーは最大値に向かう)。2つの法則を定式化。
1867(45)ヴュルツブルク大学で教授。
1868(46)王立協会の外国人会員。
1869(47)ボン大学で教授。
1870(48)普仏戦争(1871年まで)。戦闘中に怪我。鉄十字勲章。
1875(53)妻が死去。6人の子を育てる。
1879(57)コプリ・メダル受賞。
1884(62)ボン大学で学長(1885年まで)。
1885(63)講演『自然界のエネルギー貯蔵とそれを人類の利益のために利用すること』。後に論文で発表。
1888(66)貧血症のためボンで死去。
〔参考〕https://en.wikipedia.org/wiki/MAUD_Committee
オットー・フリッシュ著、松田文夫訳(2003)『何と少ししか覚えていないことだろう』吉岡書店。
Otto Robert Frisch (1979), What little I remember. Cambridge University Press.
オットー・ロベルト・フリッシュ Otto Robert Frisch, 1904年10月1日 - 1979年9月22日
リーゼ・マイトナー Lise Meitner, 1878年11月7日 - 1968年10月27日
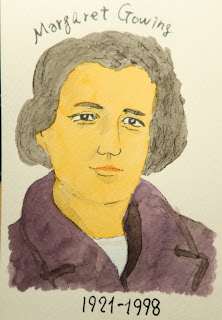





コメント
コメントを投稿