熱学の迷路~用語のごちゃつきを愚痴る:アルケーを知りたい(477)
今回の話題は(A)物理学。
▼熱学はムズイ。その理由のひとつは、用語と単位の関係が込み入っていることにある。用語と単位の関係は1対1であって欲しいのに、1対nになっている。分かっていればどうということはないのだろうけど、これから学ぶ人にとっては不親切である。
▼どんな用語があるかというと、平尾物理(つまり高校物理)では、熱量、熱容量、比熱が出てくる。単位は熱量がJ、熱容量がJ/K、比熱がJ/(kg・K)である。ここまではよいとして、計量単位令と突き合わせていくと・・・
▼込み入り、その1 計量単位令では熱量について、計量単位はジュールJ 又はワット秒W・s、定義は一ジュールの仕事に相当する熱量・・・① としている。物理量と単位が1対1ではないことに戸惑う。
▼込み入り、その2 平尾物理の巻末資料では、ジュールが表す物理量は、エネルギー、仕事、熱量、電気量であり、物理量と名称が1対1ではないことに戸惑う。単位も J = N・m = kg・m2/s2 = W・s = C・V と複数出てくる。異なる単位同士が = でつながれていることに戸惑う。
▼込み入り、その3 用語の問題。計量単位令にある比熱容量が、私が参照している平尾物理にはなくて、熱容量と比熱が載っている。計量単位令に熱容量と比熱はない。しかし、単位を見れば、比熱容量と比熱は同じことを言っていることが分かる。
【比熱容量】ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg・K) 又はジュール毎キログラム毎度 J/(kg・℃):一キログラムの物質の温度を一ケルビン上げるのに要する熱量が一ジュールであるときの比熱容量・・・②
▼込み入り、その4 平尾物理では、熱容量の単位はジュール毎ケルビンJ/Kと示されている。計量単位令にもジュール毎ケルビンがある。けど、それはエントロピーの単位として出ている・・・③
▼① 計量単位令、別表第一、第二条関係三十
② 計量単位令、別表第一、第二条関係三十二
③ 計量単位令、別表第一、第二条関係三十三
▼ところで、運動や食事ではカロリーを使う。カロリーは、計量単位令の別表第六(第五条関係)「特殊の計量」の十三で「人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量」の項に位置づけられている。計量単位はカロリー。定義はジュール又はワット秒の四・一八四倍。
カロリーを別扱いしてくれてよかった。
▼今日の人物 カロリーを「水 1 kg の温度を0 °Cから1 °Cに上げるのに必要な熱量」としたフランスの物理学者ニコラ・クレマンさん(Nicolas Clément、1779 - 1841)は残念ながら顔写真が見つからなかった。
そこで、ジュールさんやマイヤーさんと並ぶエネルギー保存則の発見者、
ヘルマン・フォン・ヘルムホルツさん(Hermann von Helmholtz 1821 - 1894) 教育▽ベルリンのフリードリヒ・ヴィルヘルム医学学校で博士(医学) 職業▽ベルリン大学他で教授 実績▽熱力学の第1法則。19世紀ドイツを代表する科学者 人脈▼多数。ハインリヒ・ヘルツ(弟子)、田中正平(物理学者。ベルリン大学に留学してヘルムホルツさんに指導を受ける)、マックス・プランク(ヘルムホルツさんより37歳年下の同僚)
〔参考〕
有山智雄et al.『中学総合的研究 理科〔四訂版〕』旺文社。
平尾淳一『総合的研究 物理』旺文社。
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Helmholtz
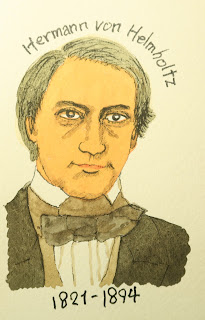



コメント
コメントを投稿