電気量の単位、クーロンC:アルケーを知りたい(478)
今回の話題は(A)物理学。
▼電気料と電気量。音は一緒。だけど中身が全然違う。電気料は現実にお金の請求と支払いが発生する話なので、測り方や計算式がはっきりと定められている。しかし、今回は後者の話。概念的な話とデータが混在している。1600年代に琥珀を擦るとものを引きつけるのはなぜか?から始まって、以来数百年にわたって多くの仮説と実験が重ねられた歴史がある。
▼中高生の勉強法で大事なのは「こういう形で試験に出る。だからこういう解き方をする」という作法を身につけることだ。脇道にそれると危険である。例えば、電子と陽子の持つ電気量は等しいのに、質量は1:1800である。これはどういうこと?などと考え始めると危ない。そういうことを考えるのは中高を終えてからで良い(笑)。で、以下、電気量のお勉強。
▼電気量は電荷量ともいう。平尾物理では「電荷によってもたらされる電気的な効果の大きさを示す量」とある。また、電荷とは「電気的な現象の根源を表す概念」。根源の話だ。では電荷を持つのは誰か?
▼電荷を持つものに電子と陽子がある。
電子1個が持つ電気量(電気素量)は、-1.602✖10のマイナス19乗である。めちゃ小さい。
陽子1個が持つ電気量(電気素量)は、+1.602✖10のマイナス19乗である。電子との違いは符号が+であること。
▼以上が前段。今回の話であるクーロンに進もう。
計量単位令では電気量の計量単位は「クーロン」になっている。定義は「一秒間に一アンペアの直流の電流によって運ばれる電気量」である。(計量単位令、別表第一、第二条関係三十四で定義されている電気量)
〔C〕= 〔A・s〕ってこと。
▼アンペアはSI基本単位だ。定義は「電気素量を十の十九乗分の一・六〇二一七六六三四クーロンとすることによって定まる電流」である(計量単位令、別表第一、第二条関係四で定義されている電流)
▼今日の人物 クーロンの単位のもとになったフランスの物理学者
シャルル・ド・クーロン(Charles de Coulomb 1736 - 1806) 教育▽メジエール王立工学学校 職業▽フランス陸軍でエンジニア 実績▽49歳のときねじり天秤を開発しクーロンの法則を発見 人脈▽キャヴェンディッシュさん(クーロンさんより先にクーロンの法則を発見していた英の物理学者。科学者の中で一番の金持ち、金持ちの中で最も偉大な科学者、と言われた人物) ピーター・ヴァン・マッシェンブレーケさん(ライデン瓶を発明したオランダの物理学者。クーロンさんが城塞建設の仕事で苦労していたとき、マッシェンブレーケさんの摩擦理論から問題解決のヒントを得た)
〔参考〕
有山智雄et al.『中学総合的研究 理科〔四訂版〕』旺文社。
平尾淳一『総合的研究 物理』旺文社。
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles-Augustin_de_Coulomb
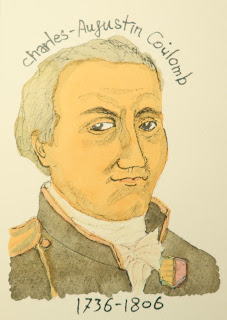



コメント
コメントを投稿