1803、ヘンリーの法則~ヘンリー(英):アルケーを知りたい(587)
今回は化学。
気体の溶解の前提は、
(1)気体は溶媒の体積が大きいほど溶けやすい。
(2)気体は温度が低いほど溶媒に溶けやすい(炭酸飲料は温めるとCO2がすぐ抜ける)。
(3)気体は圧力が高いほど溶媒に溶けやすい。
▼ウィリアム・ヘンリー William Henry 1775 - 1836 イングランドの化学者
【人物】父親は外科医・薬剤師でマンチェスター文学哲学協会の創設者
【教育】1807(32)エディンバラ大学で医学博士
【職業】病気のために医師として勤務できなかったためエジンバラ大学で化学の研究者
【業績】1799(24)『Elements of Experimental Chemistry』を発行、好評を得て版を重ねる
1803(28)ヘンリーの法則を発表
1808(33)コプリ・メダルを受賞
【同じ年生まれの人】
シェリング Schelling 1775 - 1854 ドイツの哲学者。ドイツ観念論を代表する哲学者。
アンペール André-Marie Ampère 1775 - 1836 フランスの物理学者。電磁気学の創始者のひとり。
マリュス Etienne-Louis Malus 1775 - 1812 フランスの軍人、物理学者。反射光、偏光が専門。ホイヘンスの光の理論を証明する実験を行った人物。
【ネットワーク】
トーマス・ヘンリー Thomas Henry 1734 - 1816 イギリスの外科医・薬剤師。ウィリアムの父。スパークリングミネラルウォーターを開発、販売。現在『Thomas Henry Tonic Water』のブランドで販売されている。
トーマス・パーシヴァル Thomas Percival 1740 - 1804 イギリスの医師。労働衛生と医療倫理の祖。▼ウィリアム・ヘンリーの師匠。
宇田川 榕菴 うだがわ ようあん 1798 - 1846 津山藩(岡山県津山市)の藩医で蘭学者。ヘンリーが1799年に出版した『Elements of Experimental Chemistry』がドイツ語に訳され『Chemie für Dilettanten』となり、それがオランダ語に訳され『Leidraad der Chemie voor Beginnennde Liefhebbers』となり、それを榕菴が和訳して『依氏舎密』として発行。これにラヴォアジエの水素燃焼実験図など新しい情報を加えたのが『舎密開宗(せいみかいそう)』
【似顔絵サロン】
〔参考〕
『理科年表2022』
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Henry_(chemist)
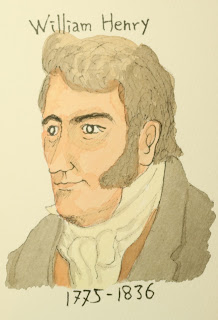





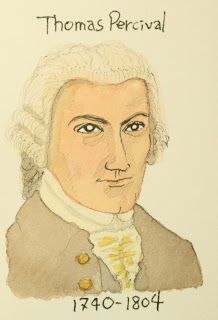




コメント
コメントを投稿