1842、ドップラー効果~ドップラー(墺):アルケーを知りたい(648)
今回は物理学。
▼ドップラーのここが面白い:ドップラー効果の元は、星の光が星と観測者の相対速度に依存するのではないか、という1841(38) の研究から生まれたものだった。 ドップラー効果を音で実験したのがパロット、星の光のスペクトルの青方偏移と赤方偏移に着目したのがフィゾー。パロットの実験がドップラー効果を分かりやすいものにしてくれた。
▼ドップラー Christian Andreas Doppler 1803年11月29日 - 1853年3月17日
オーストリアの物理学者。
【人物】?
【教育】ザルツブルクで哲学を学ぶ。
【職業】1829(26) ウィーン工科大学で助手、数学と物理学を学ぶ。
1841(38) チェコ工科大学で教授。
1847(44) 鉱山と森林のアカデミーで教授。
1850(47) ウィーン大学物理学研究所で所長。
【業績】1842(39) ドップラー効果の数式を発表。
【ネットワーク】
ウンガー Franz Joseph Andreas Nicolaus Unger 1800年11月30日 - 1870年2月13日 オーストリアの植物学者。ダーウィンの前に進化論を提案。▼ウィーン大学実験物理学研究所でドップラーの同僚。
バロット Christophorus Buys Ballot 1817年10月10日 - 1890年2月3日 オランダの気象学者。▼1845年、列車に乗ったトランペット奏者がGの音を吹き続け、それを絶対音感を持った音楽家が聞く実験をしてドップラー効果を証明。
フィゾー Armand Hippolyte Louis Fizeau 1819年9月23日 - 1896年9月18日 フランスの物理学者。1849年、回転歯車を用いて光速度を測定した。▼1848年、光のドップラー効果を発表。星のスペクトル線の青方偏移と赤方偏移を予測。
メンデル Gregor Johann Mendel 1822年7月20日 - 1884年1月6日 チェコの司祭。メンデルの法則。遺伝学の祖。▼ウィーン大学時代、ドップラーやウンガーの弟子。
【似顔絵サロン】
〔参考〕
『理科年表2022』
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Doppler
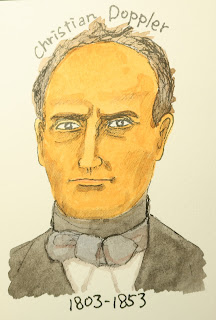







コメント
コメントを投稿