内藤 丈草~定型詩でアルケーを知りたい(856)
今回は俳句。
感想 蚊帳は夏、障子は冬、夏の月、3対2で夏の勝ち。
▼内藤 丈草 ないとう じょうそう 俳人・蕉門十哲の一人
【プロフィール】
1662(寛文2)年、愛知県犬山市生まれ。父親は武士。
1676(14) 武士・俳諧師の寺尾直竜に仕える。
1680(18) 名古屋で穂積元庵に漢学を学ぶ。
1688(26) 出家。『奥の細道』の旅から帰った芭蕉と出会う。芭蕉の依頼で『猿蓑』の跋を執筆。
1693(31) 芭蕉の拠点、滋賀大津の義仲寺無名庵で暮らす。
1694(32) 芭蕉が死去。「骸は木曽塚に送るべし」の遺志で義仲寺に埋葬。
木曽殿と背中合わせの寒さかな(島崎又玄)
1695(33) 義仲寺に仏幻庵を結び、大行脚や経塚建立を担う。
大はらや蝶の出てまふ朧月
1704(元禄17)年3月29日、仏幻庵で死去。42歳。
【キーワードと感想】
義仲寺無名庵 義仲寺は滋賀県大津市にある寺。無名庵は寺の別名。木曾義仲の墓がある。
【ネットワーク】
木曾(源) 義仲 みなもと の よしなか 1154(仁平4、久寿元)年 - 1184(治承8)年3月4日 武将。源頼朝の軍勢に討たれた。▼墓所は滋賀県大津市の義仲寺。芭蕉は義仲寺が好きで滞在や句会の開催に使用。芭蕉の遺言で墓所は義仲寺。丈草ら蕉門のメンバーが管理。
各務 支考 かがみ しこう 1665(寛文5)年 - 1731(享保16)年3月14日 俳諧師・蕉門十哲の一人。▼芭蕉の遺書を代筆。「骸は木曽塚に送るべし」の遺志に従い、亡骸を丈草がいる義仲寺に埋葬。
【似顔絵サロン】
〔参考〕
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%97%A4%E4%B8%88%E8%8D%89
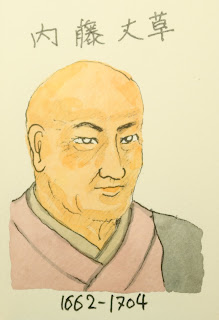





コメント
コメントを投稿