藤原 敦頼~百人一首でアルケーを知りたい(951)
▼思ひわび さても命は あるものを 憂きにたへぬは 涙なりけり 82
感想 この歌の作者の道因法師は、歌人としてのデビューは高齢者になってからのよう。それまでは役人として勤め上げたよう。立派な生き方だ。伊能忠敬を連想する。92歳の長寿の人であったことがめでたい。
1090寛治4年 - 1182寿永元年 92歳。
平安時代後期の貴族・歌人・僧。俊恵の和歌の会のメンバー。
1160(70) 太皇太后宮大進清輔歌合に参加。
1170(80) 左衛門督実国歌合に参加。
1172(82) 藤原清輔が催した暮春白河尚歯会和歌に参加。
広田社歌合を勧進。出家。道因と称する。
1175(85)と1179(89) 右大臣兼実歌合に参加。
1178(88) 別雷社歌合に参加。
月を詠んだ歌。季節の移りを感じさせる素晴らしい歌。
月のすむ空には雲もなかりけり うつりし水は氷へだてて
月みればまづ都こそ恋しけれ待つらむとおもふ人はなけれど述懐の歌とてよめる
いつとても身のうきことはかはらねど 昔は老をなげきやはせし
月と老いを詠んだ歌。
身につもる我がよの秋のふけぬれば 月みてしもぞ物はかなしき
【道因にまつわる話】
鴨長明『無名抄』に出てくる道因のエピソード
その1:道因は歌への執心が深く、秀歌を得ることを祈って住吉神社に月参した。
その2:藤原俊成が『千載和歌集』に道因の和歌を十八首採用した。すると道因が俊成の夢に現れて涙を流して喜んだ。これを俊成が憐れに思いさらに二首加え二十首にした。
『歌仙落書』の道因評 風体義理を先としたるやうなれども、すがたすてたるにあらず。すべて上手なるべし。
【ネットワーク】
藤原 清輔 ふじわら の きよすけ 1104長治元年 - 1177治承元年7月17日 平安時代末期の公家・歌人。藤原顕輔の次男。百人一首84:ながらへば またこのごろや しのばれむ 憂しと見し世ぞ 今は恋しき
俊恵 しゅんえ 1113永久元年 - 1191建久2年 平安時代末期の僧・歌人。父は源俊頼。百人一首85:夜もすがら もの思ふころは 明けやらで ねやのひまさへ つれなかりけり
藤原 俊成 ふじわら の としなり 1114永久2年 - 1204元久元年12月22日 平安時代後期~鎌倉時代初期の公家・歌人。『千載和歌集』に道因の和歌を20点採用。百人一首83:よのなかよ 道こそなけれ 思ひ入る 山の奥にも 鹿ぞ鳴くなる
鴨 長明 かも の ちょうめい 1155久寿2年 - 1216建保4年7月26日 平安時代末期~鎌倉時代前期の歌人・随筆家。1212年『方丈記』。1211-16年『無名抄』。
【似顔絵サロン】
〔参考〕
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E6%95%A6%E9%A0%BC
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/douin.html
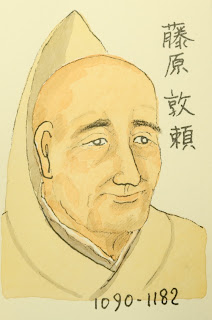


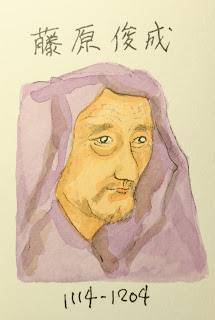




コメント
コメントを投稿