飛鳥井 雅経と承久の乱~アルケーを知りたい(983)
▼京都で生まれ育ち、10歳から27歳まで鎌倉暮らし、以降は京都に戻り時々鎌倉と往復。源頼朝ファミリーと仲良く、後鳥羽上皇の歌壇メンバーというネットワークの人。
▼雅経が死去したのは1221年4月5日、その4月の下旬に後鳥羽上皇が兵を集めて承久の乱を起こした。
▼雅経の和歌はどれも百人一首に採られた歌から感じられる雰囲気が共通している。ここでは月を詠んだ歌をいくつか見た。
▼飛鳥井 雅経 / 参議雅経 あすかい まさつね
1170嘉応2年 - 1221承久3年4月5日 51歳。
平安時代末期~鎌倉時代前期の公卿・歌人。
父親は源義経の同盟者・難波頼経の次男。
1180(10) 従五位下。蹴鞠の才能を祖父の頼輔に見出され、特訓を受ける。
源頼朝・義経兄弟が対立、父は一貫して義経側だったため伊豆に配流。
京都にいた雅経は鎌倉に下向、頼朝から可愛がられ猶子になる。
頼家・実朝と親交。
大江廣元の娘と結婚。
1197(27) 後鳥羽上皇の命により上洛。侍従。院の蹴鞠の師。以後も鎌倉幕府の招きで鎌倉へ度々下向。
1198(28) 鳥羽百首・正治後度百首・千五百番歌合・老若五十首歌合・新宮撰歌合などの歌会・歌合に参加。
1201(51) 和歌所寄人、新古今集撰者の一人。
後鳥羽院の評:雅経は殊に案じかへりて歌詠みしものなり。手だりとみえき。
1208(58) 後鳥羽院から蹴鞠長者の称号を授かる。
1211(61) 鴨長明を実朝の和歌の師匠に推挙。一緒に鎌倉に下向して実朝に紹介するも師弟関係は成立せず。
1218(48) 従三位。
1220(50) 参議。
1221(51) 4月上旬に死去。下旬に承久の乱。
▼雅経の和歌
たづねきて花に暮らせる木の間より 待つとしもなき山の端の月
*花を見にやって来て一日過ごしていると、木々の間に見える山の端から月が昇っていた。
建保四年、後鳥羽院に百首歌奉りける時
秋の夜の月にいくたびながめして 物思ふことの身につもるらむ
*秋の夜、月を繰り返し眺めてしまう。物思いすることが身に積もっている。
葦辺ゆく鴨の羽風もさむき夜に まづ影こほる三島江の月
*葦辺で動く鴨の羽音が寒く聞こえる夜。三島江の水面が凍って月が映る。
かげとめし露のやどりを思ひいでて 霜に跡とふ浅茅生の月
*冬の月が、浅茅生に露が降りていた時期を思い出して、霜にその痕跡を聞いているよ。
影やどす露のみしげくなりはてて 草にやつるる故郷の月
*草が増えて露が多くなったぶん、月はやつれてしもうた。
建久三年正月十四日、賀茂社へまうでけるに、月はくまなくて雪うちちりければ
まだしらずそのかみかけてふりぬれど 月と雪との夜半の白木綿
*雪は昔から降るものだけど、夜半、賀茂社の白木綿に月光が差し雪がちらつく風景はこれが初めてだ。
【似顔絵サロン】
〔参考〕
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E4%BA%95%E9%9B%85%E7%B5%8C
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/masatune.html#VR
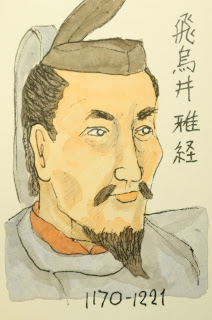









コメント
コメントを投稿