藤原家隆と承久の乱~アルケーを知りたい(984)
▼家隆は、43歳で後鳥羽上皇の推しで『新古今和歌集』の撰者になった歌人。
▼承久の乱の後、後鳥羽上皇が隠岐に配流された後も、上皇の歌合せに参加して後鳥羽歌壇の一員であり続けた。
▼大阪湾に沈む夕日が見える場所に夕陽庵を結ぶ、というライフスタイルがお洒落。大阪湾は昔は「ちぬの海」と呼ばれていた。子供のころ安心院町の「ちの」という地区に住んでいたのを思い出した。
▼藤原 家隆 ふじわら の いえたか 従二位家隆。
1158保元3年 - 1237嘉禎3年5月5日 79歳。
鎌倉時代初期の公卿・歌人。和歌の師匠が藤原俊成。
1177(19) 侍従。
1186(28) 西行勧進の「二見浦百首」に参加。
1187(29)「殷富門院大輔百首」「閑居百首」に参加。
1192(34) 九条良経主催の「六百番歌合」に参加。 九条良経の家隆評:末代の人丸。
1195(37) 後鳥羽院歌壇のメンバー入り。後鳥羽院の家隆評:秀哥ども詠み集めたる多さ、誰にもすぐまさりたり。
1201(43) 従四位下。和歌所で寄人。『新古今和歌集』の撰者。
1206-20(48-62)宮内卿。
1221(63) 承久の乱。後鳥羽院は隠岐に配流。
1226(68) 「家隆後鳥羽院撰歌合」で判者。
1235(77) 従二位。
1236(78) 隠岐で後鳥羽院が主催した「遠島御歌合」に詠進。
1237(79) 出家。摂津国四天王寺で夕陽庵を結び、ちぬの海(大阪湾)に沈む夕日を好んだ。現在、大阪市天王寺区夕陽丘。
▼藤原家隆の和歌
旅歌
野辺の露うらわの波をかこちても 行くへもしらぬ袖の月かげ
*野の草の露や岸辺の波のせいにしてみたけれど、塗れた袖に映る月影はどこに行くのか
明けばまた越ゆべき山の峰なれや 空行く月の末のしら雲
*夜が明ければこれから越える山の峰の空に雲を引き連れた月が昇っている
君が代にあふくま川のむもれ木も 氷の下に春をまちけり
*今の世に生まれ合わせ、川の流れの下の埋もれ木のようになっているけど、氷の下で春を待っているのだ
西行法師、百首歌すすめてよませ侍りけるに
いつかわれ苔の袂に露おきて しらぬ山ぢの月を見るべき
*いつの日か私も僧衣姿になり、名も知らぬ山の月を見て落涙するのでしょうね
滝の音松の嵐もなれぬれば うちぬるほどの夢はみせけり
*瀧の音や松の嵐にも慣れてきたら、うとうとして夢を見るようになったことよ
つたへきて残る光ぞあはれなる 春のけぶりに消えし夜の月
*遠い道のりを伝わって残った光に感慨を覚える 夜の月が春霞でも光を残すように
さびしさはまだ見ぬ島の山里を 思ひやるにもすむ心ちして
*見たこともない島の山里をイメージしているとそこに住んでいるような寂しい気持ちになった
春日山おどろの道も中たえぬ 身をうぢばしの秋の夕暮
*春日山の茨の道が途中で絶えた。秋の夕暮れ時、宇治橋に佇んでいる
契りあれば難波の里にやどりきて 波の入日を拝みけるかな
*ご縁があったので難波の里で暮らしている。ここからは波に沈む夕日が拝めるんだ
【似顔絵サロン】
〔参考〕
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%AE%B6%E9%9A%86_(%E5%BE%93%E4%BA%8C%E4%BD%8D)
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/ietaka_t.html#VR
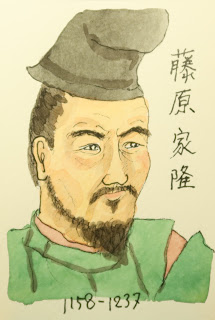








コメント
コメントを投稿