大中臣能宣の歌~アルケーを知りたい(1013)
▼能宣は目で捉え、耳で聞き、鼻で香った感覚を和歌にする匠の人。御垣守の歌は、かがり火の炎とか火が映し出す衛士の影が目に浮かぶよう。
▼大中臣 能宣 おおなかとみ の よしのぶ
921(延喜21)年 - 991(正暦2)年8月
平安時代中期の貴族・歌人。大中臣能宣朝臣。大中臣頼基の子。三十六歌仙の一人。
平兼盛・源重之・恵慶らと親交。
951(30) 和歌所寄人。『万葉集』訓読と『後撰和歌集』撰集。
960(39) 天徳内裏歌合に参加。
973(52) 伊勢神宮祭主。
986(67) 正四位下。
▼大中臣能宣の和歌と*勝手に解釈
みかきもり衛士のたく火の夜は燃え 昼は消えつつものをこそ思へ
*皇居の衛兵のかがり火が夜は燃え、昼は灰になって消えている。私のもの思いも同様だ。
もみぢせぬときはの山にすむ鹿は おのれ鳴きてや秋をしるらむ
*紅葉の風景がない常磐の山にいる鹿は、自分の鳴き声で秋の訪れを知るのだろう。
かをらずは折りやまどはむ長月の 月夜にあへる白菊の花
*香らなければ折るかどうか迷っただろう、九月の月夜の光に浮かんだ白菊の花を。
梅の花にほふあたりの夕暮は あやなく人にあやまたれつつ
*梅の花の香が漂う夕暮れ。来客かと訳もなく勘違いするばかリだ。
春の歌の中に
花散らばおきつつも見む常よりも さやけく照らせ春の夜の月
*花が散るならばいつもより夜更かしして眺めよう。明るく照らしてくれないか、春の夜の月。
【似顔絵サロン】
〔参考〕
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B8%AD%E8%87%A3%E8%83%BD%E5%AE%A3
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/yosinobu.html
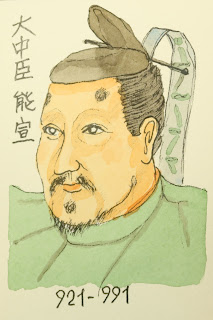







コメント
コメントを投稿