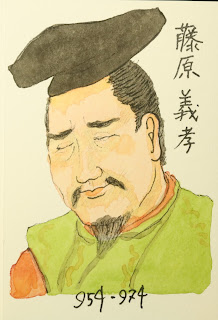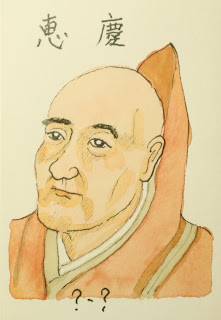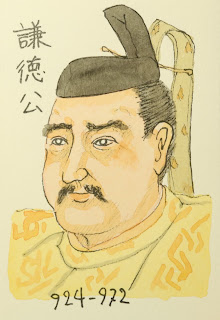藤原実方~百人一首でアルケーを知りたい(933)
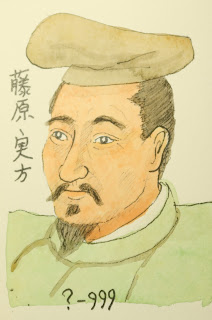
▼ かくとだに えやは伊吹の さしも草 さしも知らじな もゆる思ひを 51 感想 さしも草ときて、さしも知らじなと語呂合わせ。お灸のも草ときて、縁語のもゆるとつながる。言葉の選び方、並べ方が巧みだ。駄洒落にならず和歌の品格を保っているのがさすが。 ▼ 藤原実方朝臣 ふじわら の さねかた 959(?) - 999長徳4年1月3日 40歳。 平安時代中期の貴族・歌人。中古三十六歌仙の一人。 主君:花山天皇→一条天皇 藤原公任 ・ 源重之 ・ 藤原道信 らと交流。 972(13) 左近衛将監。 975(16) 侍従。 986(27) 内裏歌合に出詠。 994(35) 左近衛中将。 995(36) 陸奥守。 999(40) 陸奥国で巡視中、落馬事故で死去。 陸奥に侍りけるに、中将宣方朝臣のもとにつかはしける やすらはで思ひたちにし東路に ありけるものをはばかりの関 =やすらはで(ためらいもなく)東路を歩んで来たけれども、はばかりの関( 陸奥の国にある面白い名前の関所 )で気後れしたよ、という内容。 【キーワードと感想】 さしもぐさ 艾草。 お灸に使うもぐさのこと。 蓬(よもぎ)。 朝臣 あそん、あそみ。684天武天皇13年に制定された八色の姓の制度で作られた位。一番が真人(まひと)で、朝臣はそれに次ぐ位。その後、宿禰、忌寸、道師、臣、連、稲置と続く。 【ネットワーク】 藤原 公任 ふじわら の きんとう 966康保3年 - 1041長久2年2月4日 平安時代中期の公卿・歌人。大納言公任。百人一首55: 滝の音は 絶えてひさしく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ 源 重之 みなもと の しげゆき ? - 1000長保2年 平安時代中期の貴族・歌人。三十六歌仙の一人。百人一首48: 風をいたみ 岩うつ波の おのれのみ くだけてものを 思ふころかな 藤原 道信 ふじわら の みちのぶ 972天禄3年 - 994正暦5年8月20日 平安時代中期の貴族・歌人。百人一首52: 明けぬれば 暮るるものとは 知りながら なほうらめしき 朝ぼらけかな 【似顔絵サロン】 〔参考〕 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%AE%9F%E6%96%B9 https://www.asahi-ne...