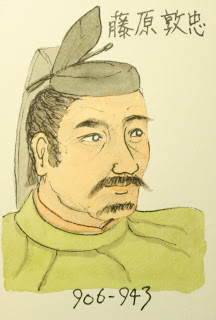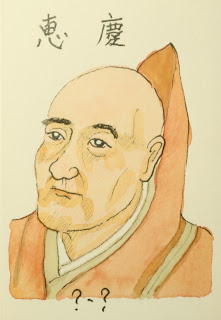清原深養父の歌~アルケーを知りたい(1025)

▼ 清原深養父 は百人一首36番歌「 夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを 雲のいづこに月宿るらむ 」の作者。 ▼深養父は琴の名手で、深養父が演奏する琴を聴きながら、 藤原兼輔 や 紀貫之 が歌を詠んだという。何とゴージャス。 ▼兼輔が詠んだ歌は「 みじか夜のふけゆくままに高砂の 峰の松風吹くかとぞ聞く 」。深養父の琴の音を峰の松風の音に喩えた。よき演奏、よき称え方、いいね。 ▼清原深養父 きよはら の ふかやぶ ? - ? 平安時代中期の歌人・貴族。 清原元輔 の祖父。清少納言の曾祖父。 908(?) 内匠允。923(?) 内蔵大允。930(?) 従五位下。 ▼清原深養父の和歌と*勝手に解釈 月のおもしろかりける夜、暁がたによめる 夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを 雲のいづこに月やどるらむ *夏の夜はまだ宵の口と思っていると明けてしまう。月は沈む間もないだろう、雲のどのあたりに月は宿をとっているのだろうね。 秋の歌とてよめる 幾世へてのちか忘れむ散りぬべき 野辺の秋萩みがく月夜を *年月を経れば忘れるのだろう。野原に咲くこれから散るであろう秋の萩を磨き上げるような月夜を。 題しらず 川霧のふもとをこめて立ちぬれば 空にぞ秋の山は見えける *川霧が麓から立ち上ると秋の山は空に浮かんでいるように見える。 題しらず なく雁のねをのみぞ聞くをぐら山 霧たちはるる時しなければ *雁の鳴き声だけが聞こえる小倉山だ。霧が晴れる時がないので。 雪のふりけるをよみける 冬ながら空より花の散りくるは 雲のあなたは春にやあるらむ *冬だというのに空から花が散ってくる。雲の向こうに春がいるのだろう。 あひしりて侍りける人の、あづまの方へまかりけるをおくるとてよめる 雲ゐにもかよふ心のおくれねば 別ると人に見ゆばかりなり *大空を通して心の交流がありますから。人にはお別れのように見えるだろうけれど。 時なりける人の、にはかに時なくなりて嘆くを見て、みづからの、嘆きもなく、喜びもなきことを思ひてよめる 光なき谷には春もよそなれば 咲きてとく散る物思ひもなし *光の届かない谷では春も他人事です。花も人も咲いてはすぐに散ってしまい、思い悩む間もありません。 題しらず 昔見し春は昔の春ながら 我が身ひとつのあらずもあるかな *昔に見た春は昔の春だよね。それを見たわが身はそのまま、ということはないな...