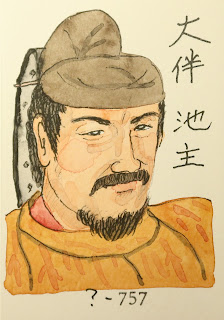万葉集巻第十八4048-4051番歌(めづらしき君が来まさば)~アルケーを知りたい(1530)
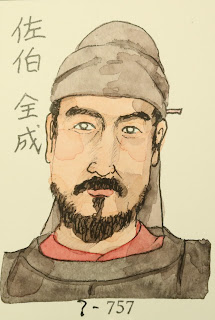
▼ 田辺史福麻呂が布勢の水海を見物するときの歌。家持は4048番で都を詠い、福麻呂は4049番で現地を褒める歌を詠う。4050番で久米広繩がホトトギス不在を詠い、雰囲気を転じる。そして4051番で家持が締める。この四首で起承転結になっている。 垂姫の浦を漕ぐ舟楫間にも 奈良の我家を忘れて思へや 万4048 右の一首は大伴家持。 *垂姫の浦を舟で遊覧するちょっとの間でも、奈良の我が家を忘れることはありません。 おろかにぞ我れは思ひし乎布の浦の 荒磯の廻り見れど飽かずけり 万4049 右の一首は田辺史福麻呂。 *思いを寄せることもなかったこの乎布の浦。実際に荒磯を廻りますと風景を見て飽きることがありません。 めづらしき君が来まさば鳴けと言ひし 山ほととぎす何か来鳴かむ 万4050 右の一首は掾久米朝臣広繩。 *珍しく貴方様がいらしているので来て鳴くように言いつけておいた山ホトトギスですが、なぜか来て鳴いてくれません。 多胡の崎末の暗茂にほととぎす 来鳴き響めばはだ恋ひめやも 万4051 右の一首は大伴宿禰家持。 前の件の十五首の歌は、二十五日に作る。 *多胡の崎には木が暗くなるほど茂っているのだから、ホトトギスが来て鳴いてくれたら、こんなに恋しがることもないでしょうに。 【似顔絵サロン】橘奈良麻呂の乱に関係した人々:佐伯 全成 さえき の またなり ? - 757 奈良時代の貴族。橘奈良麻呂から黄文王を皇嗣に立てる旨の謀反を唆されるが拒絶。乱の後、奈良麻呂の謀反を証言し自殺。 〔参考〕 伊藤博訳注『新版 万葉集四』角川ソフィア文庫。 https://manyo-hyakka.pref.nara.jp/db/dicDetail?cls=d_kanno&dataId=18